きれいないし

「たからものはきれいないしなんだ」
そういってうれしそうに石を見せてくれる長女。
どこかに行くとまずは地面をチェック。
ポケットにはたからものがいっぱい。
夫が用意した石を入れるためのケース、きれいないしのマンションみたいだね。
2009年11月21日 Posted by sunny at 04:43
言葉と体験イメージを結びつける
自分の子ども以外の子どもの成長に関わる機会が少し(本当にわずかな時間ですが)あります。
「言葉と体験イメージを結びつける」
これはすぐに子どもたちへの接し方に生かせると思うとともに、今まで何となく「体験」を共にしていただけであったことに反省しています。
私は指導者としての立場ではないのですが、それでも自主的に関わる立場であるのに、そういう点をわかっていなかった。
わが子と家庭で何かをするときにも心がけていきたいとも思います。
§ 体験的学習が重要な理由
体験的学習が重要だということは前著「絶対学力」でも書きました。また、校外に出て何かをさせることが体験的学習ではないことも書きました。体験的学習とは言葉と体験(体験イメージ)を結びつけることです。それなのに、何かをさせることが体験的学習だと思っている人がまだまだいるようです。これでは、折角の体験的学習も学力には結びつきません。正しい体験的学習が学力養成(特に吸収力の養成)に効果的である最大の理由は「分かる」の素となるイメージを言葉と結びつけてたくさん作ることができるからなのです。体験的学習は知的系統的学習に比べて圧倒的に多量の情報を提供してくれます。つまり、圧倒的多数のイメージを提供してくれるということです。私は、これらの理解の素となるイメージを原形イメージと呼んでいますが、人はこの原形イメージを持っていないと考えること・理解すること・分かることができないのです。もちろん豊かな言葉を添えて味わうようにすることが最良の方法です。言葉を通してイメージが再現されなければ応用しづらいからです。言葉が無くても原形イメージはできますが、引き出すことができないのです。ここのところを意識して指導することが学力を育てるポイントなのです。一見同じ事をしているようでも、このポイントを押さえているかどうかで全く異なる成果を得ることになるのです。 何のための体験的学習なのかを知らずに効果的な指導ができるはずがありません。無目的に指導していた人は、今一度、目的を明確にしておかなければいけません。目的が確定できていない指導者の下で行われる体験的学習は単なる時間の無駄遣いになることが多いからです。
どんぐり倶楽部HP
http://homepage.mac.com/donguriclub/trigger.htmlより
「言葉と体験イメージを結びつける」
これはすぐに子どもたちへの接し方に生かせると思うとともに、今まで何となく「体験」を共にしていただけであったことに反省しています。
私は指導者としての立場ではないのですが、それでも自主的に関わる立場であるのに、そういう点をわかっていなかった。
わが子と家庭で何かをするときにも心がけていきたいとも思います。
§ 体験的学習が重要な理由
体験的学習が重要だということは前著「絶対学力」でも書きました。また、校外に出て何かをさせることが体験的学習ではないことも書きました。体験的学習とは言葉と体験(体験イメージ)を結びつけることです。それなのに、何かをさせることが体験的学習だと思っている人がまだまだいるようです。これでは、折角の体験的学習も学力には結びつきません。正しい体験的学習が学力養成(特に吸収力の養成)に効果的である最大の理由は「分かる」の素となるイメージを言葉と結びつけてたくさん作ることができるからなのです。体験的学習は知的系統的学習に比べて圧倒的に多量の情報を提供してくれます。つまり、圧倒的多数のイメージを提供してくれるということです。私は、これらの理解の素となるイメージを原形イメージと呼んでいますが、人はこの原形イメージを持っていないと考えること・理解すること・分かることができないのです。もちろん豊かな言葉を添えて味わうようにすることが最良の方法です。言葉を通してイメージが再現されなければ応用しづらいからです。言葉が無くても原形イメージはできますが、引き出すことができないのです。ここのところを意識して指導することが学力を育てるポイントなのです。一見同じ事をしているようでも、このポイントを押さえているかどうかで全く異なる成果を得ることになるのです。 何のための体験的学習なのかを知らずに効果的な指導ができるはずがありません。無目的に指導していた人は、今一度、目的を明確にしておかなければいけません。目的が確定できていない指導者の下で行われる体験的学習は単なる時間の無駄遣いになることが多いからです。
どんぐり倶楽部HP
http://homepage.mac.com/donguriclub/trigger.htmlより
2009年11月13日 Posted by sunny at 05:35
習い事の落とし穴
長女はピアノを習っています。
習い始めた理由についてはここでは省かせていただきますが、始めたからには上手くなってほしいという気持ちを私はどうしても捨て去ることができないでいました。
でも、習い事の落とし穴を読んで「あぁそうだった」と気づいた。
もちろん心のどこかでそうだっていうことはわかっているのですが、ナゼか忘れてしまう母の愚かさ・・・。
再認識できてよかった。
何のために習い事に行かせているのでしょう。習い事に行くことを嫌がっているときに無理やりに行かせたりしていませんか。
例えば「描くこと・演奏すること」を本当に習得するには「描く技術・演奏する技術」が絶対条件なのではなくて「描きたいもの・演奏したいもの」が豊かに育つことが絶対条件です。技があっても味覚がなければ一流のコックにはなれないのと同じです。特に習い始めのころは技を習得することではなく、豊かな内面を作り上げるために味わうことが大切です。「素晴らしい絵を見ること。素晴らしい演奏を聞くこと」つまり、味わうことを最優先させなければいけないということです。上手な絵と素晴らしい絵とは違うこと、上手な演奏と素晴らしい演奏とは違うことを体験させる必要があるということです。また、習い事が忙しくて勉強できないという人が時々いますが、これもまた本末転倒しています。親鳥が小鳥に泳げるからお前は飛べなくてもいいよと言うようなものです。深い楽しみを知っていれば、練習を苦労とは感じません。練習を苦労と感じる場合は楽しむ体験が不足しているということです。練習を強要するのではなく、楽しく味わう機会を作ってあげてみてはどうでしょうか。
どんぐり倶楽部HP
http://homepage.mac.com/donguriclub/kouenkai.html#Anchor118104より
習い始めた理由についてはここでは省かせていただきますが、始めたからには上手くなってほしいという気持ちを私はどうしても捨て去ることができないでいました。
でも、習い事の落とし穴を読んで「あぁそうだった」と気づいた。
もちろん心のどこかでそうだっていうことはわかっているのですが、ナゼか忘れてしまう母の愚かさ・・・。
再認識できてよかった。
何のために習い事に行かせているのでしょう。習い事に行くことを嫌がっているときに無理やりに行かせたりしていませんか。
例えば「描くこと・演奏すること」を本当に習得するには「描く技術・演奏する技術」が絶対条件なのではなくて「描きたいもの・演奏したいもの」が豊かに育つことが絶対条件です。技があっても味覚がなければ一流のコックにはなれないのと同じです。特に習い始めのころは技を習得することではなく、豊かな内面を作り上げるために味わうことが大切です。「素晴らしい絵を見ること。素晴らしい演奏を聞くこと」つまり、味わうことを最優先させなければいけないということです。上手な絵と素晴らしい絵とは違うこと、上手な演奏と素晴らしい演奏とは違うことを体験させる必要があるということです。また、習い事が忙しくて勉強できないという人が時々いますが、これもまた本末転倒しています。親鳥が小鳥に泳げるからお前は飛べなくてもいいよと言うようなものです。深い楽しみを知っていれば、練習を苦労とは感じません。練習を苦労と感じる場合は楽しむ体験が不足しているということです。練習を強要するのではなく、楽しく味わう機会を作ってあげてみてはどうでしょうか。
どんぐり倶楽部HP
http://homepage.mac.com/donguriclub/kouenkai.html#Anchor118104より
2009年11月11日 Posted by sunny at 03:56
どんぐり倶楽部とシュタイナー
私がシュタイナーを知ったのは、今から14年ほど前。
図書館で偶然手に取った「ミュンヘンの小学生」(著者:子安美知子)がきっかけでした。
それからは子安美知子さんの本やシュタイナー関連の本を読み漁り、バイト代で「ルドルフ・シュタイナー教育講座〈1〉/教育の基礎としての一般人間学」というお高い本まで買った記憶があります。
どんぐり倶楽部のHPでシュタイナーとの接点というページを見つけたのは数日前。
ホント、どんぐり倶楽部のHPって迷路みたい^^。
何で今まで気づかなかったんだろう・・・わりとマメにチェックしているのにな~。
そこに、シュタイナーに教育に関する糸山先生のコメントというページがあり、その中に私の長年の漠然とした疑問を的確にご意見されている方がおり、驚いた。
同じことを思うひとっているのですね。
そんな中で一番心に響いたのはこの一文。
●しかし、何度もいいますが、子供を「よく見る」ことができれば、理論は不要です。
じんわりじんわり響いています・・・。
図書館で偶然手に取った「ミュンヘンの小学生」(著者:子安美知子)がきっかけでした。
それからは子安美知子さんの本やシュタイナー関連の本を読み漁り、バイト代で「ルドルフ・シュタイナー教育講座〈1〉/教育の基礎としての一般人間学」というお高い本まで買った記憶があります。
どんぐり倶楽部のHPでシュタイナーとの接点というページを見つけたのは数日前。
ホント、どんぐり倶楽部のHPって迷路みたい^^。
何で今まで気づかなかったんだろう・・・わりとマメにチェックしているのにな~。
そこに、シュタイナーに教育に関する糸山先生のコメントというページがあり、その中に私の長年の漠然とした疑問を的確にご意見されている方がおり、驚いた。
同じことを思うひとっているのですね。
そんな中で一番心に響いたのはこの一文。
●しかし、何度もいいますが、子供を「よく見る」ことができれば、理論は不要です。
じんわりじんわり響いています・・・。
2009年11月03日 Posted by sunny at 03:45
遊びが変わった。
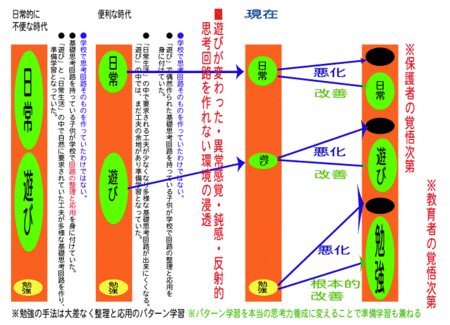
http://homepage.mac.com/donguriclub/kairo_kiki.pdfより
昔は、遊びも含めた日常生活の中で工夫するという
思考回路作成をする機会がたくさんあった。
ところが、今は、
日常生活の中で工夫するという自然に思考回路が作られる
機会そのものが少なくなった。
こうなると、
今までは、殆ど思考回路作成に悪影響の無かった
(遊びなどでリセットされていたので悪影響への抵抗があった)
宿題等(勉強:パターン学習の学習塾や反復形の家庭学習用教材も含む)が、
これまでにない悪影響を与えることになってくる。
もちろん、単純回路の反復使用や高速使用では
一つの思考回路さえも増加させることは出来ない。
つまり、今は、日常生活&遊び&勉強のどの場面でも
自然に思考モデル(思考回路)を増加させることはできないという
三重苦の中に子供達はいるのです。
さらには、知育という全く役に立たないどころか、
思考の原形となる原形イメージの獲得の邪魔になる
知的系統的学習が低年齢化していることで、
誰もが持って生まれた才能を壊滅的に破壊する学習が進んでいる。
このような早期教育も含めると、
子供達は人類はじまって以来の四十苦(八方塞がり)の中で、
文字通り思考力養成から遠ざけられている。
これでは、「考える力」は育たない。
もちろん「生きる力」も育たない。
どんぐり倶楽部HP
http://homepage.mac.com/donguriclub/sum_up_01.htmlより


